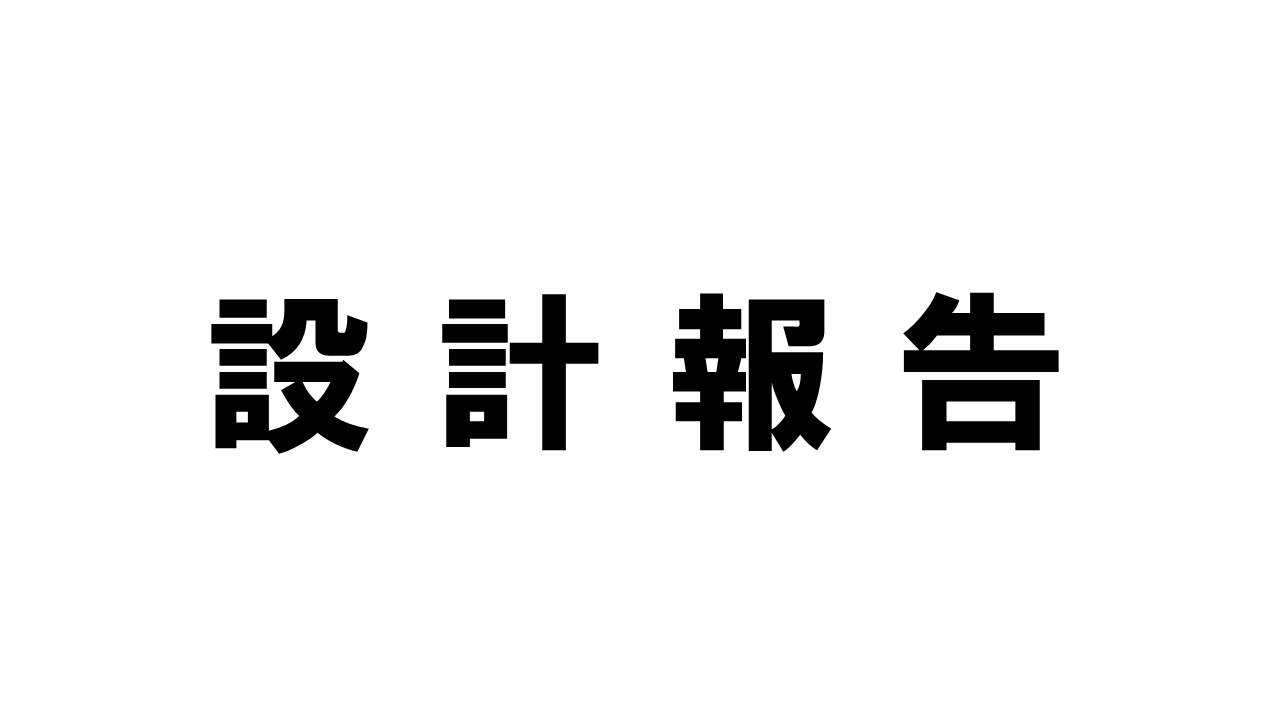
- Group全体設計
- Date2025.09.12
S-320設計のあれこれ① -最適な設計が正解ではない-
はじめに
時の流れは早いもので、代替わりしてから1ヶ月が経過しました。9月になってもまだまだ暑い日が続きますが、ここ最近は夜間の気温が抑え気味なので心地よく寝れる日が続いています。
夏はやはりあついのであまり作業は進めていません。基本的には設計者が設計を進めていくシーズンになります。
班員の皆さん元気にしてますか?お掃除という素敵な素敵なお仕事があるのでぜひ作業場に顔を出してほしいです。お待ちしております。
自己紹介をしていませんでした。S-320全体設計の さいたま です。 プロ埼玉県民として活動しています(ちがいます)。
TBTを知らない方のために、TBTの設計についておおまかに説明します。基本的には翼構造、翼空力、フレーム、駆動、フェアリング、プロペラ、電装の設計を分担しており、それぞれが自分の担当部分の設計をするといった形になります。操舵というのもありますが、少し複雑なので今回は説明を省きます。
私は全体設計という役職ですが、これは設計者のリーダーとして機体全体の設計をまとめるといった役職になります。基本的に全体設計が何をするかはその代の全体設計によって大きく変わりますが、機体全体の挙動や運用等について設計者に問題点を投げかけることが大きな仕事ではないかなと思っております。
この記事について
他の活動日誌と雰囲気が違うと思いますが、この記事は設計の進捗報告と、設計を進めていくうえで全体設計として考えたことをまとめていきます。あまりオブラートには包まず、話し合ったことや思ったことをつれづれなるままにまとめていこうと思うので、この記事を読んで新しい視点を持っていただけると幸いです。
設計自体は4月くらいから考え始めていたので、そのころからこのような記事を書いていこうと思っていましたが、とある理由のために今まで温めていました。交流会資料*が公開され、設計について鳥人間関係者へ公開したので、遅くなりましたが活動日誌にも設計について書き連ねていきます。
自由人なので、投稿は不定期になります。
*交流会資料とは?-春と秋の年二回、人力飛行機を製作しているチームが情報交換等をおこなう交流会が開かれる。その交流会では各団体が交流会資料という資料を作り公開する。設計の進捗や、研究、実験などをして分かったことなどがまとめられている。おふざけページもある。
人力飛行機設計の難しさと面白さ
ご存じの方がほとんどだと思いますが、TBTは2人乗り機を長い間設計しています。この話を外部の人間にすると高確率でなんで?と返ってきますが、これに対する返答にはいつも困ります。もちろん理由があって採用しているわけですが、単純な話ではないので大抵は”ロマン”という言葉で片付けてしまいます。
鳥人間コンテストで記録を出せる機体としての正解はかなり固まってきています。お金と時間を費やしてそのような機体を作れば、良い結果が得られるのは誰でもわかります。しかし、お金と時間が必要です。特に支配的なのは時間です。学生チームは製作に充てられる時間が一年間しかなく、チャンスは一回きりなので、それが鳥人間の面白さであり奥深さだと思っています。
チャンスは一回きりと書きましたが、それは嘘でもあります。鳥人間コンテストには全チーム出ることができないので、まずは出場権を勝ち取るところから始めなければならないわけです。人によって様々ですが、鳥人間コンテストに出場するために活動をしている人間がほとんどなので、大会に出場するための設計というのも大切になるという訳です。
2人乗り機は他のチームがやっていない唯一無二の機体なので、製作難易度はかなり上がりますが、鳥コンに出場して記録を残すという意味では重要な訳です。この機体が鳥人間として最適か?と言われたらそうではないです。理論上は2人乗りでも性能の良い機体を作ることができますが、運用、機体運搬、コスト等を考えていくと限界があります。
記録を目指すために1人乗り機などに方向転換する。このような案も悪くはありませんが、導入一年目で上手く行くかという話です。2人乗り機をより進化させるか、1人乗り機などに大きく転換をして記録更新を狙うか的な内容は毎年悩むところではありますが、大きく転換をすることによって想定外の事故や破損が起きたら終わりな訳ですから、結局2人乗りを継続した方が良いという結論に落ち着きます。今年もそうです。
-設計の正解とは何なのか?
これは歴代の設計者が誰もが一度は悩んだことのある問題だと思います。ただ、人力飛行機の世界をより深く知っていただくために、最適な飛行機の設計が正解という訳ではないということを知っていただきたいです。この話が人力飛行機の、鳥人間の面白さの根幹の部分であり、この文化が長く続いている理由だと私は思います。
2人乗りの意義とは?
S-320の機体設計を進めていくうえで、この大きな壁にぶつかりました。上の章に書いたことを考えていくと、2人乗りの意義とは何か?という疑問が浮かんできます。設計者目線では別によいのですが、客観的にTBTの機体を評価するとなったときに、2人乗りをわざわざ採用している意味が伝わらないとなぜ続けているのか、が分からないです。短期的に2人乗りを採用するのであれば、新規性を求めた機体という意味は分かりますが、長年やってくるとそうはいきません。何か別の”理由”が必要になってきます。
今までのTBTの機体は1人乗り機と似たような形状となっていました。専門的な言葉を使うと、ダイダロス型というやつです。
パイロットが2人なので馬力は2倍になりますが、重さも2倍になるので結局変わりません。それ以上に、部材にかかる力が2倍になるのでより強固に大きく作る必要があり、製作難易度が上がります。1人乗りの機体をベースにして2人乗りとして運用できるような形へ変えていったのが今までの機体なので、なぜわざわざ2人乗りを採用してるの?と言われたら、性能的にメリットになるようなことを返すことができません。
そこで、2人乗りしかできない機構を取り入れて、2人乗りを続けている理由を作ろうとしました。
双発串型2人乗り機
2人乗りの意義を求めた結果として出てきた案が”双発串型2人乗り機”です。
今まではコックピットの前方にプロペラが1枚ついている機体でしたが、これは双発なのでプロペラが2つになり、それぞれがコックピットの前後に付きます。この機構になると、2人のパイロットの駆動経路が独立するので駆動的なロスが少なくなります。今まではパイロットが2人いることによって駆動的なロスが発生していたことが2人乗り機のデメリットだったので、この機構にすることによってそれを解消することができます。また、前後で推進を分けることにより機体周辺の流れが整流され、空力的な利点があります。つまり、2人乗りでしか採用できない機体かつ、今までの機体より性能が良くなる(可能性がある)ので、このような機体設計にすれば2人乗り機を採用する意義ができるわけです。
ただ、そんな簡単に問題が解決できるうまい話はありません。もちろんしっかりとしたデメリットもあります。
一番大きなデメリットは、機体運用の難易度がぐっと上がることです。今まではTF(=テストフライト)で機体を着陸させるときに、”ストッパー”という役職の人が走って機体に追いつき、コックピット後方にあるハンドルを全体重をかけて引くことで機体を止めていました。
2人乗りなので1人乗り機よりも機体重量が重く、このようにしないとなかなか止まりません。
前述したとおり、双発串型機にするとコックピットの後ろにプロペラが来るのでそのような芸当ができません。
安全な運用ができないことは、チームとして何としても避けなければならないことです。負傷者を出すことや、施設等に損害を与えることはもってのほかなので、安全に運用できることに確証を持てない機体設計は良くない設計となります。
今まで通りの運用ができないならば、運用方法を変えて安全に運用する方法を考えなければなりません。
設計者の葛藤
-今までの設計にするか、新しい設計にするか
S-320の設計者はこの議題に3ヶ月以上の時間を費やしています。
ここまで読んでくださった方は、この問いの難しさについて少しはわかっていただけると思いますが、そう簡単に結論を出せるものではありません。安定した記録を得ることを求めるのか、大会出場することに焦点を当てるのか、後の代のためには何をするべきか、設計者のプライド、設計の面白さ、無事故で運用すること…考えなければならないことが非常に多いです。
学生チームなので、チャンスは一回きり。
部員の意見も蔑ろにはできません。我々は何を求めて、どのような結果を望むのか。それに向けてどのような手を打つのが最善なのか。満足して引退することができるのか。すべての結果を大きく変える選択を今しなければなりません。
それぞれの案に対する意見は、次回の記事でまとめていこうと思います。
現状の設計者が抱える葛藤と、人力飛行機の難しさ、それゆえの面白さをこの記事で知っていただけたら幸いです。
それではまた次回~